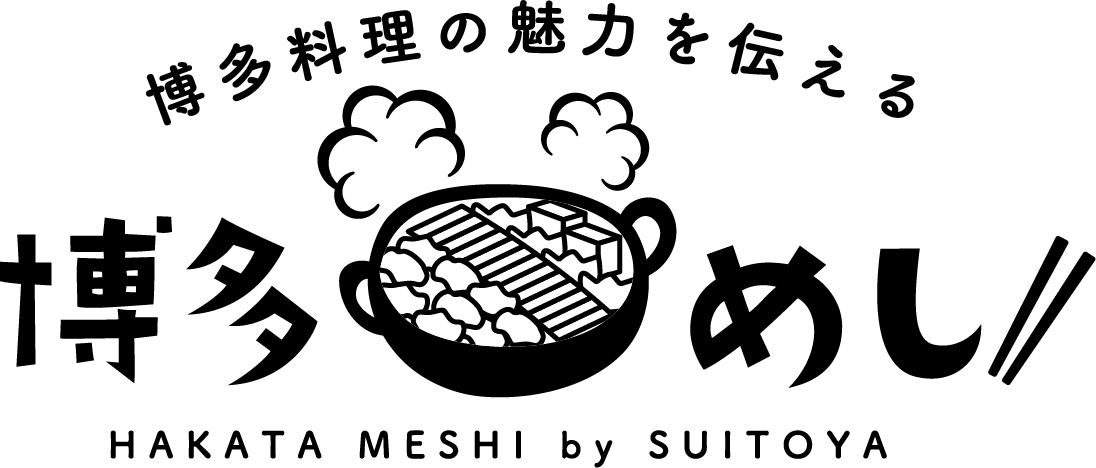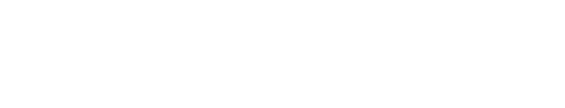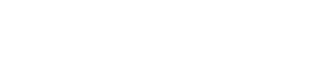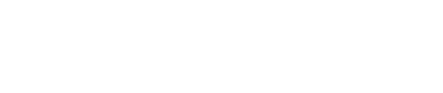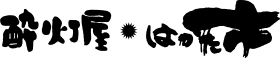もつ鍋の発祥と歴史
もつ鍋の発祥
第二次世界大戦が終わる昭和20年(1945年)の頃、初代・松隈ハツコさんが営む「万十屋」でもつ鍋の前身が生まれたと言われています。
その名の通り、昭和18年(1943年)までは饅頭屋として営んでいましたが、夫が兵役で戦地に行っていることや、餡や粉の材料が尽きてしまい、閉店することにしたそうです。
何を売っていいかわからないという状況の中、目につけたのは行商が売り歩いていた牛や豚の内臓でした。
さっそく内臓料理に挑戦しましたが、まるで雑巾のようでとても食べられるものにはなりませんでした。
しかし、料理の研究を諦めず、試行錯誤した結果、内臓と野菜と醤油などの調味料をアルミ鍋で合わせて焼いた「ホルモン焼き」ができました。
余談ですが、内臓肉は一般的には捨てられていた部位であることから、「捨てる=放るもん」というのがホルモンの由来になったと言われています。
この頃は醤油や砂糖を味付けとした”すき焼き風”の味だったそうです。
醤油風味で香ばしい味わいが周辺で話題となりました。それが今のもつ鍋のはじまりと言われています。
その後の歴史
ホルモン焼きが広まってきた当時は戦時中だったので、民間では鉄類が回収されてしまい、アルミ鍋で代用していました。
昭和37年ごろ、アルミ鍋から鉄鍋に変わったそうです。
また、キャベツが多く取れるようになった時期でもあり、もつ・にら・キャベツ・ちゃんぽんというお馴染みの組み合わせになったとされています。
この頃はまだすき焼き風の味付けでしたが、しばらくして現在のようなスープのもつ鍋になりました。
その後数年間で、もつ鍋が博多名物として日本全国で爆発的に人気となりました。その要因は、食通で知られる作家の壇一雄の長男である壇太郎の存在でした。
彼は食べ歩きをしながら全国にもつ鍋を紹介し、話題を集めました。昭和60年ごろからマスコミの取材が増え、メディアで取り上げられるようになり、人気に人気を呼んで広まっていったとされています。
もつ鍋が普及する前は、人から人への口コミでもつ鍋の味が親しまれて来ました。今は福岡の至る所で「もつ鍋」の暖簾や提灯が並び、すっかり博多の味として浸透しました。安価で野菜がたっぷり使われているので、ヘルシー鍋料理と女性の間でも人気になり、もつ鍋ブームが起きています。